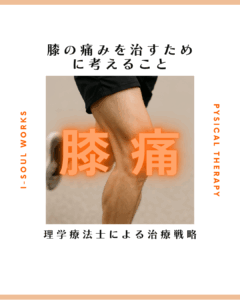
【はじめに】
「右膝の痛み」を抱えておられるクライアント様(40代/女性)にインソールを作製させていただきました。どのようなことを考えてインソールを作製しているのかをわかりやすく解説していきます。症状を緩和するために、理学療法士がどのように治療プロセスを立案しているのかを歩行動画を踏まえて解説をすすめていますので、一般の方から医療従事者の方までよかったらご一読ください。
→『当店のサービス詳細』は(←)こちらから!!
【インソール作製後のご感想】
今回アイソウルワークスの伊佐地さんにインソールを作成してもらいました。
インソールを作成してもらおうと思った動機は「子どもと思いっきり走っても、後から痛くならない膝にしたい。」という想いです。
私は両膝とも靱帯と半月板の手術を受けています。
自分でトレーニングやケアをしながらスポーツ(バスケットボール、フラッグフットボール)も継続できていたのですが、子どもが生まれてからは、スポーツをする機会が減り、自己ケアの優先順位も下げてしまっていました。(=サボってました…)
そんな中、子どもが大きくなって走り回るようになり、一緒に遊んでいると、膝の調子がイマイチに…。腫れたり、しゃがみにくくなったり、痛みがでたりといった状況でした。そんな状況を改善させようとトレーニングを再開しましたが、足関節にも手術歴があり、足部がぐらついたり、思うような動きができなかったりともどかしさを感じていました。
この状況をどうにかしたいと、伊佐地さんに連絡しインソールを作成してもらいました。
結論から言うと、作成してもらって本当によかったです。
膝の調子は良い方向に向かっています。
足部が整うので体重をかけた状態でのトレーニングもとてもやりやすくなりました。
いつ洗うか悩むくらい、毎日愛用しています。
先日、子どもの小学校で行われたイベントのリレーで思いっきり走ることもできました。
鬼ごっこも出来ています。
そろそろフラッグフットボールも再開しようかなと前向きに考えています。
やりたいことができるって改めて大切だなと感じています。
伊佐地さんは病院やスポーツ現場など様々な場所で経験を積まれ、アイソウルワークスのオフィシャルサイトにもたくさん載っている通り、自身が学ばれたことを勉強会などでしっかりとアウトプットされていたりと、常に自己研鑽を行っている、信頼しておまかせできる方だと思います。
もし身体の痛みが原因で、やりたいことが出来ていない、諦めようとしてしまっている方がおられたら、ぜひ相談に行ってみてください。
【主訴と既往歴の分析】
「右膝の痛み」の要因を考えていく上で最も大切にしているのが、「過去の病歴や既往歴」です。過去に起きた不調や痛みは身体になんらかの影響を与え続けているケースが非常に多いです。生理的許容範囲から脱してしまったわずかな関節のズレ(骨と骨のズレ)や筋や筋膜などの軟部組織の硬さや柔軟性の低下、そして各筋の筋力低下などが要因となり、「良好な姿勢や円滑な動き」を妨げてしまい、身体各部位でストレスの吸収と分散が不十分となり、右膝に過度なストレス集中が引き起こされている可能性が考えられます。
まずは、「現在」である痛みの出る部位と、「過去」であるこれまでの病歴などを含めた経過を照らし合わせ、過去と現在をつなげる分析を行うことがとても重要となると考えています。その分析を行いつつ、現状の右膝に加わる過度なストレスの要因を明確にしていく機能評価を実施することで、治療の方向性を明確にしていきます。
<病歴と手術歴>
中学〇年生 腰椎椎間板ヘルニアによる右下肢の痺れ
右足関節内反捻挫 →靭帯縫合術
高校〇年生 右前十字靭帯断裂+半月板損傷 →再建術
20××年 左アキレス腱断裂 →縫合術
20××年 左前十字靭帯断裂+内側半月板損傷 →再建術+半月板縫合術
★「スポーツ傷害膝 × コンディショニング」(←クリック!!)
このように多くの怪我と手術を繰り返されています。
まずは、怪我をしやすい体質である可能性を考えます。先天的な関節の弛緩性が強かったり、逆に関節が硬かったり、姿勢の左右差、柔軟性・筋力の左右差が過度であるなど身体機能をチェックする前に様々な可能性を予測します。また、一度の怪我や手術によって本来有している機能が変わってしまう場合が多く、これまでの自分の身体や動きではないといった違和感を生じるケースも多いです。怪我前の機能を確認することは難しいですが、健側と比較する中で、正確な機能評価による現在の機能を把握することが重要となります。
既往歴からの推察では、ヘルニアが要因で考えられる感覚障害や筋力低下、右足の内反捻挫術後の可動域や筋力の低下が右膝の運動性に影響を与え、右側前十字靭帯損傷を招いた可能性が考えられます。下肢の筋力低下は膝関節の動揺につながり、足関節の可動性低下は膝関節の過度な回旋運動を引き起こします。次に、膝の手術後は再建靭帯の再断裂を防ぐため、スポーツ活動に復帰するため、リハビリテーションを実施します。高強度なトレーニングを繰り返し、健側よりも強い筋力を目指します。しかし、スポーツ活動を終え、トレーニングを行わないこと、日常生活レベルの運動負荷で生活することで、筋力低下が起こります。また、年齢を重ねることで筋力の低下が起きることを考えると徐々に右下肢の筋力が低下し、柔軟性も低下することで気づかない間に、健側である左下肢に依存した動きが優位となります。その状況下でスポーツ活動を行うと更に左下肢への依存度が高まり、左側のアキレス腱に過度なストレスがかかってしまったことが予測できます。アキレス腱の断裂は、下腿後面筋である腓腹筋とヒラメ筋の筋機能を大きく低下させ、地面をしっかりと前足部で蹴ることが難しくなります。そうなることで、足関節を円滑に使えなくなり、急なストップ動作やジャンプ系動作などのパフォーマンスが低下しやすくなります。また、地面をしっかりと足裏で踏ん張る機能が低下することで、隣接関節である膝関節が過度に動くこと(動揺)や動きの制御機能を膝周囲筋に依存することにつながります。よって、左膝の前十字靭帯断裂と半月板損傷は、アキレス腱断裂による機能低下が要因のひとつであると考えることもできます。
そして、現在の症状です。「走る」動作を行うことで右膝に痛みが出るため、思い切って子供と楽しめないもどかしい思いがあるとのことでした。特に、右膝の痛みの部位は、「膝関節の外側」でした。
なぜ、その部位に痛みが出現するのか、そのヒントは動作の中、特に歩行や走行の中でしか確認できません。痛みの部位は、触診することで圧痛など局所症状は確認できますが、「なぜその部位、その組織に痛みが出るのか」は、動きの観察および分析をしない限り、明確にはなりません。痛みの部位にどのようなストレスが加わっているのか、どの機能的な問題がその部位にストレスをかけてしまっているのか、を機能評価により明確にさせることで、はじめて効果的な治療方針を立案できます。
今回は、インソールの作製をご希望として来られましたので、十分な機能評価はできませんでしたが、簡易な機能評価と歩行分析によって、何を修正すべきかを推察していきたいと思います。
【歩行分析と問題点の解釈】
まず、裸足歩行です。痛みが出るのは右膝の外側ですが、この動画の歩行では痛みは出ていません。ですが、走る運動時に感じる痛みの要因となる身体機能は歩行動作の中に観察でき、改善に向けた治療戦略を立てるための多くのヒントが得られます。
この動画を観て、まず気になる点は「左下肢への体重移動が不十分」であり、特に「左足関節運動」に問題があり、片脚支持相への荷重モーションと蹴り出し時の円滑な背屈運動ができていないことが観察できます。これは、主に左アキレス腱断裂による足関節運動の協調性の低下と筋力の低下(遠心性収縮能)が考えられます。また、左膝関節がX脚(外反位)となりやすく、接地と同時に膝の外反モーションが強くなり、過度な下腿の前傾および内側傾斜を認めます。左前十字靭帯損傷の術後でもあることから筋機能低下の影響も考えられますが、この動きが過度となると再断裂の危険性もあるため、体幹と股関節レベルのトレーニングをはじめ、膝関節のニュートラル位での運動機能を高めるための下腿後面筋のトレーニングの必要性も感じます。ただ、ひとつ元来有している身体特徴があり、左下肢の脚延長を認め、右脚より左脚が長いアライメントを呈しています。それによって、左側の膝や股関節、足関節をわずかに屈曲させることで脚短縮を作り、左右の身体バランスをとるため、膝の外反モーションが強くなっている可能性も考えられました。このように左下肢での荷重コントロールが不十分となることで、「右下肢への依存度」が高まります。ただ、右下肢はヘルニアからの痺れや足関節内反捻挫による手術、そして前十字靭帯損傷による手術も経験していることから、機能としては十分ではないことが予測できます。ヒトは機能が良い側の脚に頼りがちです。痛みがなくても、不安定な脚に頼ることはせず、頼りがいのある脚に依存しやすいです。そのため、右脚への負担が増えることが予測でき、その負担を減らすことが痛みの軽減につながると推察できます。歩行の中で、右下肢に体重がのっていく際に、右骨盤が上方に突き上がる動きを認めます。これは、右の股関節に円滑に体重が乗せられず、股関節から大腿部の外側の筋群に過度な筋活動を生んでしまう動きとなります。更に、左脚が脚延長していることから左脚から右脚に体重が移動する際に右外側方向に力が加わりやすいため、それを制御するためにも外側の筋群の筋活動が必要にもなってきます。結果、右下肢の外側の筋群に過度なストレスが加わり、右膝の外側部に疼痛が出現するメカニズムが推察されました。これはランナーの方がなりやすいと言われる腸脛靭帯炎(ランナーズニー)と似た障害発生メカニズムと言えます。大腿部や膝外側にある大腿筋膜張筋および腸脛靭帯、外側広筋、それらに連結する筋膜系の硬さや柔軟性、滑走性の低下が、その筋の骨の付着部に牽引ストレスが生じ、微細損傷が起こることで痛みとして動作中に出現し、運動後も炎症が起こっているため痛みを生じさせます。
足部に注目してみると、足部の外側での荷重が優位となっています。特に右側はつま先がまっすぐになりやすく、足部の剛性を高めようとする動きが確認できます。通常は、つま先は少し外側を向く(Toe-out位)となりますが、Toe-straightやToe-in位となる場合、つま先が内を向いているように観察できます。股関節の支持性が低下している場合にこのような足部の動きが生じることが多く、股関節の支持性低下を足部機能で代償していることが考えられます。更に、つま先が内を向くこと(Toe-in位)となることで足関節の背屈運動が制限されてしまいます。足関節の背屈運動制限は、膝関節の運動に悪影響を及ぼします。動画を観ると、片脚支持期の後半の蹴り出し相の前からつま先が急激に外を向いて蹴り出しを迎えます。急激なつま先の外向き運動(Toe-out運動)は、同時に下腿骨の急激な外旋運動が誘発され、結果、膝関節を急激に捻ること(外旋強制運動)になります。膝関節に過度なストレスが加わることが動きを観てもわかると思います。この場合、足関節の背屈運動を円滑に促通するために何をすべきかを考えなければいけません。そこで「インソール」が重要なツールとなります。足関節の土台となっているのは足部です。その足部機能のベースとなっている「アライメント(形状)」を変えることで、外側荷重となっている荷重位置を内側に誘導していきます。ここで重要なのは、ただアライメント(形状)を変えるだけではなく、「動きを変える」ことです。そのため、足のアライメントを構成している骨をどのように誘導すれば、促通したい動きになるのかを「評価」します。この評価がインソールを作製する際にもっとも重要であり、「足の型を採って作製するインソール」との大きな違いとなります。当店では、テーピングやパッドを使用して何度も歩いてもらって、どうすれば問題となっている動きが修正でき、痛みが出ない動きとなるのかを明確にしてインソールの形状を決定していきます。これの技術は、理学療法士として姿勢や動きを観察・分析しているからこそできるものかもしれません。とても難しい技術にはなりますが、この作業を繰り返さないことには「本当に効果の出る良いインソール」が作れません。
インソールを作製して挿入した歩行動画もありますので、動きの変化をご確認ください。今回は、インソールのみの介入になりますが、「柔軟性の改善」や「筋機能の改善」に向けたアプローチを行うことで更なる機能向上、怪我の予防が図られ、家族とのかけがえのない素敵な時間を共有していただけることを期待しています。
【最後に】
この投稿を快く承諾いただいたクライアント様に深く感謝いたします。そして、貴重なご感想もいただきありがとうございました。
【お問い合わせ】
まずは、お電話やメールにてお気軽にお問い合わせください。
以下のボタンをクリックください。

